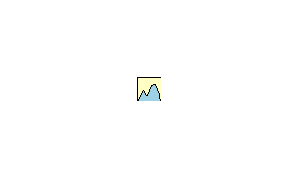| 記録 |
昨年秋、宮ヶ瀬から臨み途中で撤退した丹沢主稜縦走のリベンジを行いました。今回は、若干登降差が少ない逆ルートを選択。
前日に車で西丹沢に入り、大石キャンプ場のバンガローを借りました。翌日からオープンの予定で、まだ準備中とのこと。自分で掃除してくれればOKという条件で、なんと2人で2400円、翌日登山中の車駐車代一泊いれて2900円の激安でした。管理人さんは夜かえってしまい、無人のキャンプ場はなかなか不気味でした。 |
出発点の板小屋沢に掛かる橋 |
|
|
まだ冬枯れの木々の石棚山 |
翌朝誰もいないキャンプ場をあとにして、快晴の西丹沢を出発。箒沢から稜線まではかなりきつい登りで、標準時間よりかなり遅れて稜線上の石棚山に到着しました。
西丹沢の麓は既に緑に覆われる季節ですが、稜線から上は冬枯れのままの寂しい様子でした。その代わり、富士山や南アルプスの白い稜線がきれいに見渡せます。 |
|
この稜線からは、西方面に幾つも重なる山脈の稜線がきれいに見渡せます。
手前から、
西丹沢の畦が丸付近
道志山塊の御正体山、菜畑山
三ツ峠、御坂山塊
南アルプス
左に振ると富士山も見えますが、この場所からは木の枝の間でした。 |
西方に重なる山脈 |
|
南アルプスを望遠で撮影しました。左下の写真は、おそらく、右のピークが間ノ岳、中央の小高いあたりが農鳥岳ではないかと思います。
そのまま右に振っていくと(右下の写真)、日本第二位の高峰、北岳が見えます。南アルプス縦走は、ずっと我家の山行候補に入っていてなかなか実現できませんが、ここに限らず西丹沢のあちこちから綺麗な稜線が遠望できます。 |
|
|
大休止の後、檜洞丸を目指して尾根道を登ります。ここから先、檜洞丸までは、さほどきつい登りはありません。
山頂が近づいてくると、バイケイソウの群落地が現れます。植生保護の為、木道が作られています。すれ違い用なのか、所々が複線になっています。
あと一・二ヶ月すると一面緑の葉で覆われますが、この日はまだ土から芽がのぞき始めたばかりでした。 |
バイケイソウ群落地の木道 |
|
|
冬枯れで明るい檜洞丸山頂 |
昼前に檜洞山頂に到着。標準時間からはかなり遅れ、檜洞丸まで約4時間でした。
檜洞丸の山頂はブナの巨木があり、緑の季節にはやや鬱蒼とした感じもありますが、まだ葉を付けておらず、明るい山頂でした。ここでもブナの立ち枯れは進んでおり、ちゃんと葉が出てくるのか、ちょっと心配になります。
青ヶ岳山荘で、5年前の恩返しをついに達成。財布忘れで借りた700円のコーヒー代を支払い。500円にまけてくれました。 |
|
このあと蛭ヶ岳までがキツーい登山となりまた。痩せ尾根や鎖場があり、体力があればさほど危険ではありませんが、ここまででかなり体力消耗していましたので、二人には大変でした。
何とか明るいうちに蛭ヶ岳に到着。午後4時でした。これ以上遅くなるとかなり危険で、余裕をもって出発できてほっとしました。 |
神奈川県最高峰
360度あけっぴろげの蛭ヶ岳山頂 |
|
|
丹沢縦走路の峰々 |
山頂から東側を望むと、明日歩行予定の東丹沢の峰々が見渡せます。
左の写真のスカイライン部分に、左から、丹沢山、不動ノ峰、塔ノ岳が見えます。中央左から右に向けて蛭ヶ岳・丹沢山間の縦走路が伸び、不動ノ峰を経て丹沢山に至ります。
蛭ヶ岳山荘はそこそこ込んでいて、夕食、朝食は3班に分かれて出されました。狭い場所で窮屈な就寝。蛭ヶ岳山荘では、ワンセグ携帯でTVが見れました。 |
|
翌朝丹沢山を目指して早めに出発し、朝のうちに丹沢山に到着。
日本百名山・丹澤山と標識が立っています。深田久弥の「日本百名山」の一つに数えられていますが、この本の中では丹沢山を含む丹沢山地中央の山々の総称とされています。

泊まった蛭ヶ岳山荘 |

新装成ったみやま山荘 |
|
明るく穏やかな丹沢山山頂 |
|
|
初日、臼ヶ岳から見上げた蛭ヶ岳 |
二日目、鬼ヶ岩から見上げた蛭ヶ岳 |
|
ここから丹沢三峰の縦走に入ります。アップダウンの繰り返しが多くどれがどの峰かわかりにくいため、各峰の山頂標識を目にするまで、いったいいつ終わるのか、と心配になりました。
丹沢三峰山頂標識コレクション

西峰(太礼ノ頭) - 1,352m |

中峰(円山木ノ頭) - 1,360m |

東峰(本間ノ頭) - 1,345m |
三峰を超えてからはひたすら下山。かなり長いです。昨年、長男の体調不良で縦走をあきらめた引き返しポイントは、岩が立ちふさがる危険な場所でしたが、反対側から見ると思ったより楽なところでした。
大急ぎで下り、昼前には宮ヶ瀬着。バスで本厚木へ。本厚木駅前のファミレスでゆっくり昼食を取り、小田急で新松田へ、さらにバスでまたまた西丹沢まで戻り終了。長い縦走と車回収を完了しました。
帰途はいつもの鶴巻温泉弘法の湯。
|
| メモ |
主稜縦走路は、蛭ヶ岳と檜洞丸間の金山谷乗越など、痩せ尾根や崩落箇所があって危険と聞いていましたが、登山道そのものの危険性よりも、体力消耗状態で望む危険性を感じました。
西丹沢から上りその日のうちに蛭ヶ岳まで到達する予定の場合は、慣れていない場合はよく体力と相談したほうがいいと思います。滑落の危険もさることながら、明るいうちに到達できないという事態も考えられます。
|