| ランディングネット(1) |
渓流釣りで使う木製のランディングネット(玉網。写真の右上2つ)を手作りで作ってみました。
製作過程の記録写真を残していませんでしたので、ざっくりした手順と完成品だけご紹介します。
詳しい作成手順を説明したサイトがネットにたくさんあり、参考にさせていただきました。検索してみてください。ネット部分は購入しましたが、糸で編んでいる人もいます。 |
我家の玉網達 |
|
| 材料・道具 |
ヒノキ材(フレーム用)3枚 ・・・極薄(2mm程度)・細長(1cmx90cmくらい)
木板(グリップ用) ・・・フレーム材の幅と同じ(1cmくらい)厚さ
ネット
編紐 ・・・ネットをフレームに固定する糸
ヒートン
エポキシ系接着剤
木材用塗料、クリアラッカー
タコ糸
ヤスリ、紙ヤスリ
ジグソー
木工用ドリル
彫刻刀 |
|
| 製作 |
フレーム材の癖付け
フレーム用ヒノキ材を1日ほどお風呂の残り湯に浸し、曲がりやすくします。薄く細長い材料なのである程度曲がりますが、より柔らかくします。
紙や木でフレーム形状の型枠を作り、3枚束ねたフレーム用ヒノキ材をフレーム型枠に沿って曲げます。クリップやタコ糸で型を固定し、そのまま乾燥させます。乾燥が終わると、ヒノキ材に曲がり癖が付き、接着しやすくなります。
グリップ材の切り出し
グリップの型を紙でつくり、グリップ材の木板に書き写します。割れないように慎重に、糸鋸やジグソーで型を切り出します。 |
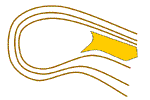
グリップ材の切り出しと
フレーム材のくせ付け |
組み合わせ、接着
三本のフレーム材の裏表、グリップ材のフレーム接着面にエポキシ系接着剤を塗り、重ね合わせて束ねたフレーム材をグリップ材に組み合わせ、完成型を作ります。
ガッチリ接着されるように、フレーム材とグリップ材部分、フレーム部分をそれぞれタコ糸でグリグリとしつこく巻き、固く結束します。あとで削り落としますので、接着剤がタコ糸にくっついてしまっても、グチュグチュにはみ出しても、全然問題ありません。 |
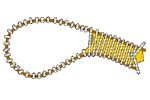
フレーム材とグリップ材
の接着。 |
成形
エポキシ系接着剤がよく固化した後、タコ糸を引き剥がします。
グリップの最下部でグリップ材とフレーム材とを一緒に切り落とし、一体化した最終形に成形します。
またヤスリや紙ヤスリで全体についたエポキシ樹脂のでこぼこを削り落とします。これで一旦形が出来上がり、完成が見えてきました。 |
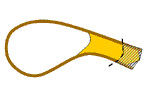
グリップ成形と
エポキシの削り落とし |
穴あけ
フレーム側面の中心線上に、ネットを固定するための糸通し用の溝を彫刻刀で慎重に真っ直ぐ掘ります。
また溝の中に、同じく糸を通すための穴を、細いドリルでフレームの側面に点々と等間隔であけて行きます。グリップ部分にも左右に1つづつ、輪の外側から内側にフレーム材とグリップ材を貫通するように穴を開けます。 |
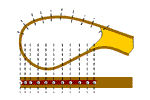
フレーム側面に、
ネット固定糸用の
溝掘りと穴掘り |
塗装
木目が綺麗に見える塗料を選んで塗り、乾燥させた後ヤスリで研磨し、塗装面を滑らかにします。この作業を何度か繰り返した後、クリアラッカーで仕上げます。綺麗な塗装面を作るためには、塗料の塗布と研磨の繰り返しを十分に行いますが、上塗りするから大丈夫といって毎回の塗装面研磨を怠けると、最後は結局でこぼこが目立ってしまいます。
仕上げ
塗装で塞がった糸通し穴をドリルで再度貫通させます。事前にサイズを調整して縫ったネットを糸(編紐)でフレームに固定し、最後にグリップにヒートンを差し込みます。ヒートンの木ネジが塗装面を突き破り、そこから木材に水が浸み込みそうなので、ねじ込み部分にもう一度ラッカーを塗っておきました。完成です。ヒートンにランディングネットクリップをつけておくとそれっぽいです。 |
|
結構な数の手順が含まれるので、子供にも幾つか作業を分担してもらいました。
接着剤の固化と塗装の乾燥時間を含めると、土日だけ作業するとして数週間かかってしまいます。成形過程もさることながら、塗装段階で時間と手間が掛かります。見た目の美しさを目指すなら、やはり塗装で手を抜かないことが大事です。反省点でもあります。
我が処女作では濃い目の塗料を選び、重ね塗りもかなりしつこくやったので、結局木目は全部見えなくなってしまいました。またネットの縫いつけ部分もちょっと粗い仕上がりです。綺麗なとはお世辞にもいえませんが、第1号なのでこんなものでしょう。十分実用的で愛着がわきそうなランディングネットが出来上がりました。 |
自作木製ランディングネット1号 |
|
| ランディングネット(2) |
ヒノキのフレーム材が余ったので、もう1本作りました。
先の折れたキリが工具箱の底に入っていましたので、このキリの柄をそのままグリップにしました。
また、箪笥の底に25年くらい入ったままコヤシになっていた混紡のメッシュのTシャツがありましたので、これをジョキジョキと切ってネットにしました。色もいい感じです。若かりし日がよみがえってハサミを入れるときは若干躊躇してしまいましたが、Tシャツの方もこのような復活を遂げることができるとは想像していなかったと思います。 |

在りし日のメッシュTシャツ |
|
|
フレーム成形、接着、塗装などの製作過程はランディングネット(1)とほぼ同じですが、穴あけ溝掘り、グリップ成形などの工程がありませんでしたので少し簡単でした。フレームとグリップの接続部分を自然な形状を残したまましっかり接続させることと、フレームをまん丸に仕上げるのには多少工夫を要しました。しずく型の普通の木製ネットよりもフレームの成形が難しかったです。
廃物廃材利用のエコネットの完成です。横文字系のフライフィッシングではなく、テンカラや餌釣りの渓流釣りに似合いそうな雰囲気です。 |
自作木製ランディングネット2号 |
|
| 番外編・ランディングネット・セット |
海釣り用の玉網をちょっとだけ改造し、レイクトローリングなど大物トラウト用ネット、エリア用、磯・エギング・防波堤釣りなど海用振り出し玉網、使う機会はありませんがシーバス用ギャフ、と色々組み合わせて姿を変えるランディングネット・セットを作りました。
海釣り用振り出し玉網
(45cm折りたたみフレーム+振り出しロッド)
これが一番元の姿。振り出しの柄は5.4mまで伸びます。元々付いていたナイロンモノフィラメントのネットは少し硬く使いにくい気がしたので、柔らかめの編紐ネットに付け替えてあります。ところが、柔らかいネットは水中に入れたときに形が崩れて少し魚を入れにくいときがあること、魚のヌル・臭い・イカスミが付きやすいこと、またフックが引っかかって取れにくくなることが極たまにあることが分かりました。モノフィラのネットは何かの拍子に捨ててしまっていたので、編紐のまま使っています。今ではさほど気にならなくなっています。
|
 |
大物トラウト用ネット
(45cm折りたたみフレーム+タワシの柄)
廃品のお風呂掃除用タワシのアルミの柄を使い、先端に玉網用連結金具をエポキシ系樹脂で固定し、振り出し玉網のフレームとネットをつけました。大きなネットは湖でのマス釣りに重宝します。万一(?)大物が来ても安心です。このネットの良いところは、海釣り用には良くある4つ折の折りたたみフレームなので、たたんで柄からはずすと全部リュックサックやロッドケースに入ってしまうという点です。
|
 |
エリア用ネット
(35cm折りたたみフレーム+タワシの柄)
大物マス用と同じタワシの柄に、径の少し小さいアルミフレームとゴムネットを付けてあります。ゴムネットで、リリース制エリアで魚体を傷つけずリリースできます。このフレームはちょとだけ工作してあります。ゴムネットの適合フレーム径は35cm程度でエリア用に程よいものですが、このサイズに合う小さめの折りたたみフレームが見つかりません。そこで、中古釣具店で45cmの標準サイズを安く買ってきて、4つ折りの1つ分を切り縮めて、3つ折りにしました。ジャストフィットしています。当然ザックやケースに入ります。
|
 |
シーバス用ギャフ
(ギャフ+タワシの柄)
タワシの柄につけてある連結用金具のネジ径は規格サイズなので、別売りのギャフがそのままねじ込めます。ボートやウェーディング、低い堤防など水面の近い場所でのシーバス釣りにもってこいかなと思って準備しましたが、ギャフで上げたくなるようなチャンスはまだ訪れていません。 |
 |
|
| 感想 |
安物の市販木製ネットはすぐに塗装が剥がれたりつやが無くなったりしますが、この自作ネットはしつこい塗装のおかげか、完成時のつやを保ち続けています。見た目は良くなくても、非常に軽くしっかりしており、実用上問題無しです。工程数の割には完成までの時間が掛かりますが、子供にも手伝わせる機会が多く、完成時の達成感がありました。
番外編の方は、元々は小さく折りたためる大きなネットがトラウト用にもほしかったことと、ケチってプチ改造してみただけのものですが、結果的にさほど安くはなかったと思います。買ったほうが安くて使い勝手がいいかもしれません。いいものは高くても本当に使い勝手が良く長持ちもします。工作の楽しみと、自作モノで釣ったゾという自己満足の範囲のものでしょうか。
|