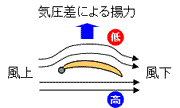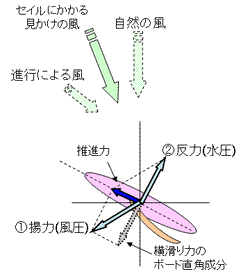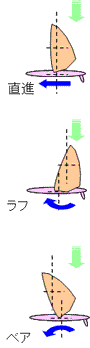ウィンドサーフィン 相模国野外育児記~子供といろいろアウトドア編
ホーム > アウトドア色々~ウィンドサーフィン
| ウィンドサーフィン(ボードセーリング) | ||||
|
||||
| サーフィンは、とりあえず乗れるようになるまで何ヶ月もかかると聞きますが、ウィンドサーフィンの場合は、波・風の条件や、コーチに問題が無ければその日のうちに乗れてしまいます。我家はコーチに少々難がありますが、子供たちもとても気に入ったようです。 | ||||
| ゲレンデ | ||||
| 東京湾側、相模湾側とも、ウィンドサーフィンのゲレンデやショップがたくさんあります。かつては江ノ島より西の鵠沼方面でも見かけましたが、ウィンドサーフィン人口の減少(多分ですが)であまり見ることがなくなってきました。 相模湾側の鎌倉、逗子、東京湾側の津久井浜などが主なスポットですが、我家は横浜市内唯一という砂浜が広がる、金沢区の海の公園に出かけています。ここのメリットは、遠浅、波穏やか、風穏やか等々で入門者向けであることです。 逗子、鎌倉も湾内の比較的穏やかな場所で、スクールも沢山ありますので、入門・練習に適していると言えます。津久井浜はやや上級向けのようです。 |
||||
|
||||
| ここのメリットは、先にあげた点以外にもいくつかあります。まず、大きな駐車場が併設されていますので、海水浴シーズン以外は駐車場が確保しやすいです。春の潮干狩り時はやや人出が多いので早めの到着が良いです。料金も上限が設定してあって、朝から一日とめて1500円で足ります。湘南方面に比べると、ですが、周辺の道路の渋滞も軽いですし、横横や湾岸でアクセスも良いところです。バーベキュー場が整備されていて、皆で出かけてワイワイやるだけでもお勧めの場所です。あけっぴろげの砂場だけでなく、涼しい木陰もあります。 公設の艇庫がありますが、艇庫会員ではなくてもボード洗い場、温水シャワーが100円玉数枚で利用できますので、我家のように年間の限られた季節に数回だけ、という不定期利用者にも便利な場所です。ボード洗い場で道具も人もきれいに潮を落し、そばの草むらでしばらく干したあと片付けてしまえば手入れ完了です。 |
||||
| 道具(ギア、エキップメントとも) | ||||
|
||||
| 悩ましいのは、中上級者になるとスピードの出やすいスラロームボードなどを使用することがほとんどですが、逆に入門者の練習に浮力の小さいこれらのボードが使えないため、どんなタイプのボードをいつ買うかという問題がある点です。何度も買いなおすのは大変なので、レンタルとスクールでしっかり上達してからスラロームを買うか、又ははじめは入門者用を知り合いに譲ってもらったり中古で済ませたり、というのが落しどころです。もちろん、さほどのめりこむのでなければ入門者用でいつまでも楽しんでもいいと思います。子供を誘うのが目的であれば、スクールでしっかり練習してからゆっくり購入を考えれば良いと思います。 | ||||
| ボード ウィンドサーフィンを楽しむ目的やスタイルによっていろいろ種類があります。強風下を短く軽いボードでかっ飛ばすスラローム、波に乗ってジャンプなどを競うウェーブやフリースタイル、速度を競うコースレースなどがあります。何れもスタイルがハッキリしていて入門者用には向いていません。 最近は、特に目的を絞っていない、いろいろなスタイルの中間的位置にあるフリーライドというカテゴリや、幅が広く、短く、また容量があって安定しているエントリーモデルが入門者用向けに販売されています。私がやっていた頃はオールラウンド艇という重くて長いタイプのボードが入門用とされていましたが、最近のエントリーモデルはオールラウンド艇よりも幅広でとても安定していて乗りやすそうです。スクールでもこのタイプが使用されています。 我家では、裏庭の軒下で半永久的野ざらしになっているミストラル社のオールラウンド艇に子供を乗せています。容量(浮力)は十分ですがとにかく重く、最近の入門用よりは細身でやや不安定なので、お楽しみ用を兼ねたエントリーモデルを新たに買うかどうか、思案中です。 ボードには、裏面に舵取りのフィン(スケグ)、表面に滑走時に足を入れて固定するフットストラップが付いています。 またレース艇やオールラウンド艇には、風上へのぼり易くするセンターボード(ダガーボード)という、フィンのような大きな板が真ん中に付いています。スラローム艇などにはセンターボードが付いていないため風上への遡上性は劣ります。 随分昔の話ですが、ウィンドサーファー艇とよばれるスタンダードモデルのダガーボードは、ボードの真ん中に縦にあいたスリットに、手でダガーボードをそのまま抜き差ししていました。風下へ向かうときはダガーボードを使わないため、手にダガーボードを引っ掛けて持っていました。それ以降のモデルでは、ダガーボードが本体に収納可能になっていて、足で出し入れする機構になっています。 運搬時や保管時のボード保護のために、ボードケースも一緒に買っておくと良いです。 |
||||
| リグ ボードを除く、セイルやマストなどの道具一式をリグと呼びます。こまごましたものが沢山あり、それぞれがまた細かな部品から組み立てられていますので、そのうち一つ家に忘れてきたり無くしたりしてもセーリングできなくなることもあって、結構神経を使います。 セイル 帆掛け舟の帆ですね。透明なプラスチックフィルムとそれを囲う化繊の布などで出来ています。セイルの面積と風速の関係がバランスの取れたセーリングに非常に大事です。大きなセイルを強風下で扱うのは大変で、コントロールできなくなって飛ばされておしまい、となる可能性もあります。弱風下では、小さなセイルではスピードが出ず楽しくないか、或いは前進することも出来なくなります。異なる面積のセールを何通りか用意できると便利です。6.0㎡前後の大きめのセイルが練習に向いていますが、少し風が強いととたんに扱いにくくなるので、スクールなどではもっと小さいセイルを使っているかもしれません。 ウィンドサーフィンの原理は飛行機の翼と同じで、翼型に膨らんだセイルの表面と裏面の気圧差が推進力になります。セイルに風を受けると片面に膨らんで、ある程度は翼形ができますが、きっちりした翼型を維持するために、バテンという名の、細くて平たい弾力性のあるプラスチック棒が、セイルの横方向に何本か作られたスリーブの中に通っています。セイルのどちら側が膨らんでいても、このバテンがきれいなカーブを作って曲がってくれます。何本かのバテンがセイルに通っていますが、セイルの横幅が広い部分のバテンのマスト側には、カム(キャンバー)といわれるマストとバテンを接続する部品が入れられ、セイルの形を維持するのに役立っています。最近のセイルは、これがなくても形状を維持できるようになっているようです。 マスト(ポール) セイルを立てて張る心棒、帆柱です。1本そのままのワンピースタイプものもありますが、かなり長いので、途中で分割できるツーピース、スリーピースタイプが一般的です。これをセイルの片端(ラフ)に作られた縦のスリーブ(マストスリーブ)に差し込みます。 ツーピース、スリーピースのマストの接続部に砂が噛んだり、塩が残ったりして抜けにくくなることがよくあります。接続時に砂が付かないように、或いは使用後にきっちりと塩分を洗い流したりする必要があります。抜けねー!と大騒ぎしていると、ありがたくも近くにいる方々が手伝ってくれたりしますが、そういう事態にならないよういつも気を使いましょう。 ブーム 人力でセイルを保持し、コントロールするための横棒です。両端がつながった2本のパイプが細長いわっかでセイルを横に挟んでいる格好になります。ブームの一方にはマストに固定するための機構、反対側に、セイルの片端をロープ(シートと言います)で引いてピンと張るための機構が付いています。ブームは、風に対抗して体をぶら下げるだけの棒ではなく、方向転換などのときにセイルをコントロールする、自動車で言えばハンドルに当たる大事な部品です。 セーリングを開始するにはまずセイルを立てて張る必要がありますが、水面に倒れたセイルを引っ張りあげるロープをアップホールラインといい、ブームのマスト連結部につながれています。アップホールラインを引っ張ってセイルを海中から引き上げることをセイルアップと言いますが、風が強いときなどはかなり体力を消耗します。上達してくると、セイルを立てたまま浅場からボードに上がりスタートするビーチスタートや、風の力でセイルと体を海中から引き上げてそのままスタートするウォータースタートを練習することになりますが、これらが出来るようになると、体力を消耗せず、格段に快適なセーリングが出来るようになります。 マストベース・ユニバーサルジョイント ボードとマスト(エクステンション)を連結するための道具がマストベースです。ボード側、マストエクステンション側ともに、連結機構のタイプがあり、コンプリートセットではなく別売品を購入するときは、それぞれ同じタイプに合わせる必要があります。 ヨットなど他のセイルを使う乗り物は、マストが船体に固定されているのが普通です。ウィンドサーフィンのマストは、前後左右に自由に倒したり立てたり出来ます。そのため非常に自由にセイルがコントロールできる構造になっていて、ウィンドサーフィンの特徴となっています。これを実現するのがユニバーサルジョイントで、マストベースに組み合わされ、ボードに連結されます。ずっと以前のものは蝶番を組み合わせたような機械的な機構のものでしたが、現在のものはウレタンなどで出来ていて、材質の柔軟性で自由な動きを実現しています。 マストエクステンション(エクステンションパイプ) マストを通す側のセイルの縁の部分(ラフ)の長さはセイルによって異なるため、ラフサイズの違うセイルを使用する際には、ちょうど良いマスト長にする必要があります。エクステンションは、マストとの連結位置を何段階にもずらすことができる、延長用のパイプです。 予備シート ヨットやウィンドサーフィンでは、道具類に使われているロープ類をシートと呼びます。セイルのラフをエクステンションの下部方向にグッと引っ張るダウンホールシート、ブームの後方にセイルを引っ張るアウトホールシートや、ブームとマストの連結部分の機構などにシートが使われています。各シート自体はそれぞれの道具に最初から付いている付属品です。 頑丈な素材で通常は切れることはありませんが、細い紐なので、古くなってきたり、知らない間に傷が出来ていたり、また極端な力がかかった場合など、切れる可能性が皆無ではありません。沖に出ているときに切れてしまうとセーリング不能になって流されてしまう可能性もありますので、我家では予備のシートをブームに巻きつけるなどして携行しています。シート以外の道具の損傷の応急処置にも使えます。 |
||||
| ウエア類 ウェットスーツ 夏場は海水パンツ一丁でも構いませんが、それ以外の季節は体温保持のためにウェットスーツ、またはドライスーツが必要です。袖や裾の長さによっていろいろなタイプがあります。 ・シーガル 半袖、長ズボン ・スプリング 半袖、半ズボン ・ショートジョン ノースリーブ、半ズボン ・タッパ 半袖、腰から上 ・ロングスリーブ 長袖のタッパ ・フルスーツ 長袖、長ズボン シーガルあたりが最も長く使えるのでは無いかと思いますが、個人個人のスタイルによります。夏前や秋口など暖かい時期だけなら、海水パンツと、薄く伸縮性がある布地のラッシュガードというウエアが適しています。どれが良いかというと、楽しむ時期と予算によりますのでなんともいえませんが、我家では今のところ長袖または半袖のラッシュガードと海水パンツで事足りる時期だけ楽しんでいます。盛夏以降は、気温が高くても、裾や袖の長いウェットスーツ、ラッシュガードを着用するとクラゲ対策になります。 ウェットスーツには浮力が少しありますし厚手の生地なので、安全面から言うと子供にはいつも着用させたほうが良いかもしれません。また、ライフジャケットがあると子供や入門者には理想的です。海水パンツ一丁でもと書きましたが、実際には素肌では日焼けで大変なことになりますので、日焼け対策は必須です。 シューズ 足の保護のために、ウィンドサーフィン用のマリンシューズが使用されます。我家では底厚で安心の釣り用のシューズも兼用していますが、全体がやや厚めなので専用の方が使いやすいです。 ボード上での足の保護の意味もありますが、海底の岩やウニなどから足裏を守るのに非常に重要です。我家の利用する海の公園はほとんど砂地で、端っこの部分に少しだけ岩があるだけですので、岩で怪我をする心配は少ないですが、海中に生えたアマモなどに付くウニを裸足で踏んづけると大怪我になる可能性があります。 アマモは魚介類の幼生の生育や水質浄化に重要な海草で、海の公園でも増殖の活動が行われているようですが、ウニが付いていることがあり、よほど注意する必要があります。セーリング中ではないですが、ウニに足を刺さされた経験が親子共々あり、木のトゲなどと違ってすっきり抜けず皮下に残ってしまい、何週間もジクジクした痛さに悩まされたことがあります。 ハーネス コルセットやパンツのような形状をしていて、ウェアを着た上に装着します。前部に下向きの大きなフックがついています。このフックを、ブームにU字型につけたハーネスラインというロープに引っ掛け、体をブームにぶら下げることができる道具です。 風を受けるセイルを腕だけで保持するのはかなり負担であり、風が強いときは限界があります。ハーネスでセイルに体重をかけることで、腕の負担を減らし、理想の角度にセイルを維持できます。ハーネスの使い方を覚えると、体が楽でスピードも出せるようになり、セーリングがとても楽しくなります。ウェアというよりもリグの一種かもしれません。 |
||||
|
||||
| ルーフキャリア 艇庫に預けない場合は車で持ち運びということになります。ルーフキャリア自体は汎用でいいですが、ボード用のクッションをつけてその上にボードを載せます。ガッチリ固定できるコードで固く縛り付けます。セイルのケースを一緒に固定しても良いですが、マストは飛び出したらこまるので、車内に入れるか、専用のマスト固定具をキャリアにつけて固定します。もちろん全部入る大型車なら問題ないです。大型車の車内に、ボードを乗せる棚をつけている方も多いです。我家の現在の車はステーションワゴンで、多少長めの車ですがさすがにオールラウンド艇は入らないので、ボードだけキャリアに乗せて、セイルケース他残りのリグは車内に押し込んでいます。 |
||||
| ウィンドサーフィンの原理 | ||||
物理をかじり始めた上の子は、フムフムと原理に関する講釈を聞いてくれましたが、下の子は逃げていきました。 |
||||
| その他 | ||||
| スクール 我家の子達は今のところ特にスクールには入れていませんが、初めての場合はスクールに参加することを是非お勧めします。県内でウィンドサーフィンが行われている海岸にはスクールを開設しているショップがかならずあります。操作自体は難しくなくても、知ってると知らないでは大違いなのがウィンドサーフィンの入門段階の技術です。 安全 スクールなら万全の対策で臨んでくれますが、それでも海の上なのでどんな事故が起きても不思議ではありません。自分の行動と結果がある程度理解・予測できる年齢でないと、沖に出ることができるウィンドサーフィンは非常に危険なスポーツだと思います。スクールで子供向けの十分な訓練を積むか、自分自身に十分な指導監督の自信がない限り、小さなお子様にはムリだと思ったほうがいいと思います。また大人並みの体力ができる中学生高校生くらいになるまでは、子供用の専用道具でなければ扱いきれません。 |
||||
| 潮干狩り ウィンドサーフィンとは無関係ですが、海の公園は潮干狩りの有名スポットで、3月から6月のシーズンにはアサリなどがざくざく取れます。無料です。 セーリングの合間に、二人の子供が遠浅の海中に寄り添って座り込み、ごそごそとアサリ漁にいそしんでいました。まだまだ子供よのうと思っていたら、水遊びの乗りではなくて、アサリをたらふく食いたいという一念だったようです。 アサリは定番の味噌汁の他、たくさん取れた時は深川丼や、オリジナルの醤油バターパスタ、ボンゴレ・ヴィオラになります。 |
||||
|
||||
| 我(家)流レシピ 我家の我流アサリレシピ2品です。こうして書いてみるとご飯と麺以外の食材が同じだな。 【深川丼】
【ボンゴレ・ヴィオラ】
|