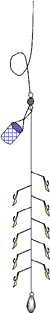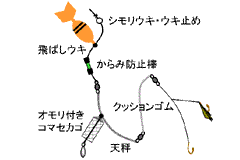| 防波堤小物 |
我家ではルアーやフライ釣りが多く、いわゆる餌釣りをすることはあまり多くないのですが、気分によって、或いは早朝出遅れたときなど、近くの港で小物の餌釣りを楽しんでいます。
港や河口などの防波堤、岸壁には、色々な魚の稚魚が集まっており、またアジ、イワシなどの小魚が回遊してきます。また小魚を狙ってシーバス、カマス、ソーダガツオといった魚食性の魚が来たり、周辺の砂地ではシロギス、根回りではカサゴやアイナメなど、様々な魚が集まっていて、簡単なタックルでのんびりと釣りを楽しむことが出来ます。
これらを全部ひっくるめて「防波堤小物」と総称しましたが、獲物も道具も様々です。 |
江ノ島・湘南港 |
|
ここには、アミコマセを使うサビキ釣り、同じくカゴ釣り、イソメなどで砂底を釣る投げ釣り(ちょい投げ)、テトラポッドやコンクリートブロック、岩礁の穴などで根魚を狙うブラクリ釣り、ルアーの5つを紹介してあります。これらは我家で実際によくやるものですが、もちろんこれだけが防波堤の釣りではありません。
サビキ釣りや投げ釣りは入門編と言える釣りなので、小さな子供と釣りで遊ぶのには最もお勧めできる釣りです。大きな折り畳み椅子を持ち込んで昼寝を決め込んだり、お弁当を広げながら釣る事も出来ます。足場が良くて規制がない所では、ガスバーナーでラーメンやうどんを作って暖かい昼食を楽しむことも出来ます。 |
| サビキ釣り |
サビキ
サビキ仕掛けは、プラスチックフィルムや魚皮などを被せた小さな疑似餌針を10本くらい連ね、最下部にオモリをつけた胴付き仕掛けです。最上部にコマセカゴを付けますが、最下部のオモリがコマセカゴになっていることもあります。カゴに詰めたアミコマセで水中に煙幕を張り魚を集め、その中で踊る疑似餌針が小さな本物の餌に見え、魚が食いつくと言うしかけです。
また疑似餌ではなく、小さな針にアミコマセを引っ掛けるトリックサビキという仕掛けも有ります。コマセブロックを専用のケースに乗せ、その上で針の付いた仕掛けを滑らせ、小さなアミを針に掛けます。最近はこちらも良く見かけます。ほぼ餌釣りです。我家では通常のサビキ仕掛けを使います。
ロッドやリールは本当に何でもOKだと思いますが、あまり硬いものは釣り味がそがれます。長めの竿なら岸に寄り切らない群にも届き、釣り易いです。短い竿と、磯竿のような5メートル級の長竿の両方があると、遠近両方攻められていいかもしれません。魚がいそうな深さまで仕掛けを沈め、竿を上下にゆっくりと動かします。これを、さびく、といいます。止めたままより遥かによく食いついてきます。
アミコマセ
かちこちに凍った状態のカタマリで売られていますので、釣りを始める前にある程度融かしておく必要があります。融かすためのバケツ、融けたアミをカゴに詰めるスプーンが必要です。アミコマセをかごに入れるときに思いっきり手が汚れますので手洗い用のバケツ、それと共用でも良いですが海水を汲むための長いひも付きバケツ、手を洗った後のきれいなタオルなども必要です。これらを一つでも忘れてしまうと結構へこみます。少し融かした状態でコマセを売ってくれる釣り具・釣り餌店もあります。
アミコマセはどうしても多少は地面にこぼれてしまいます。極めて汚く見えますし、匂いを放つので、撤収の際に必ず海水で流し落しておきます。そのためにも水汲み用ひも付きバケツは必須です。 |
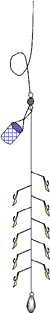
|
主な狙いはアジ・イワシなどですが、これらは回遊性なので回ってくるとバンバン釣れますが、いないときは全く釣れません。昼寝に限ります。また、真っ黒なメジナの子や黄黒縞々のイシダイの子などがいることも多く、これらは居ついていますので、居さえすれば良く釣れます。
アミコマセは、服やタックルについていると、車の中などでかなり臭います。帰って洗えばいいですが、どこかに付いたままになっているとなかなか臭いが消えませんので要注意です。その昔、使い残しのアミコマセをうっかり車の中に放置してしまい、それがひっくり返って車内に流れ出していたのを数日後に発見した、という事件がありました。車内のどこをどう拭いても、半年間はアミくさかったです。ご注意下さい。 |
| カゴ釣り |
サビキ釣りは殆ど足元で釣りますが、少し大きな魚はある程度沖合いに回遊してきます。ここでいうカゴ釣りでは、大き目のウキにコマセカゴを組み合わせて沖に投げ、エビなどの刺し餌で青物などを狙う釣りです。
マダイ、チヌ、クロの子、アジ、イサキ、ベラ類など、また遠投仕掛けでイナダ、ソーダガツオなど回遊魚を狙います。上はシマアジやヒラマサなどもカゴ釣りの対象ですが、これらの大物狙いは外洋に長く突き出た突堤や磯などがポイントになります。回遊魚の場合はやはり回ってこないことにはどうにもなりませんが、群れが来るととても楽しい釣りができます。
狙う魚のサイズで仕掛けのサイズもかなり違います。
右の仕掛けは5号ウキ、錘の入った小型のコマセカゴ、二本針の、小物向けの簡単なカゴ釣り仕掛けです。このままのセットで釣具店で販売されています。二本針の上の針は魚皮の付いたサビキ針になっています。下の針の上にガン玉が付いていて適度に沈み、こちらにエビなど刺し餌をつけます。2本針の代わりにサビキ仕掛けをつけ、遠投サビキにして釣ることもあります。
我家ではサビキ釣りの時にこの小物向けカゴ釣り仕掛けを別の長竿で一緒に出します。 |

小物仕掛け |
普段の防波堤釣りは大きめのウキとカゴの単純仕掛けで釣ることがほとんどですが、港内ではなく外洋に面した防波堤や磯など回遊魚が回ってくる潮通しのよい場所で青物の大物狙いを釣るときは、遠投ができるほど有利なので、遠投用飛ばしウキ、天秤、クッションゴムの仕掛けを、出来るだけ長めの磯竿を使用して遠投します。
大物に対応できるよう、天秤やクッションゴムを使います。また仕掛けがウキに絡まないようにする絡み防止棒(からまんぼう)などの工夫が施されます。 |
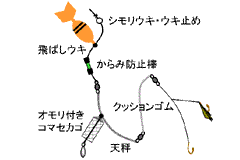
大物仕掛け |
|
| 投げ釣り |
砂浜で仕掛けを遠投しシロギスやカレイを狙うサーフキャスティングと同じような仕掛けを使いますが、防波堤から釣る時はもっと軽いオモリで投げます。ちょい投げなどと言います。
ロッド・リール
長いロッドは必要はなく、また柔らかい竿のほうが楽しいと思います。遠投するわけでもなく、大型魚とのやり取りも無いので、リールは高価なものは必要ありません。但し釣具屋さんのワゴンに入っている極端に安い物は、うるさいクリック音が止められなかったりするものもありますので、要注意です。
天秤仕掛け
ジェット天秤や海草天秤などでも良いですが、軽いおもりがセットになったものがあまり無く、最低でも15号くらいはありますので、我家では船釣りなどで使われる小型の片天秤に5号、10号といった軽いおもりをつけてちょい投げします。
キャスティングでは3本針を多く使いますが、雑魚の多いところでは、針が多くても餌取りに献上するだけなので、2本針で十分で、からみも減ってむしろ扱いやすいと思います。ボートのシロギス釣りと同じような仕掛けになります。
ということで天秤仕掛けを紹介していますが、仕掛けをぶっ込んだまま放置しておくと、水底で揉まれてかなり絡みます。キャスト時に絡みを防止するのが天秤の役目ですが、引き上げるたびに絡んでいてどうしようもなければ、中通しオモリや胴突き仕掛けにしても良いと思います。
エサ
青イソメ、ゴカイ、ジャリメ、スナメ何れでもいいですが、シロギスには柔らかく動きのいいジャリメ、スナメが有利、また濁りがあるときは青イソメ、と聞きます。ジャリメなどは投げるときに切れやすいので、遠投するときはイソメが有利になります。カレイやアイナメを期待できる時期と場所なら、岩イソメが良いです。狙いを絞るなら餌の選択はある程度重要ですが、我家の防波堤釣りはいろいろMIXが基本姿勢なので、餌もジャリメ、青イソ、岩イソとミックスで購入することが多いです。 |

片天秤
2本針仕掛け |
|
仕掛けをちょいと投げて、掛かるのを待ちます。放り込んで向こうあわせで待っても良いですが、少し遠めに投げて時々ゆっくり引いて(これもさびくと言います)、きちんと当たりをとって釣るとグッと釣果が上がります。
仕掛けをあまりに長く放置すると、フグにハリスを噛み切られて持っていかれたり、ヒトデやナマコにガッチリ食いつかれていたりしますので、適当に聴き合せしたり回収したりします。
シロギス、メゴチ、ハゼ、カレイ、ヒイラギなどと、てんぷらや塩焼きの具が主に釣れます。シャコやイイダコ、ワタリガニが釣れることも有ります。テトラやコンクリブロックが海底にあったり岩場が混じるような場所だと、ベラ類やメバルなどのロックフィッシュも掛り、さらに多彩になります。 |
大磯港のシャコ |
|
| ブラクリ釣り |
紡錘形の赤いオモリの下に短く太いハリスと針が付いているブラクリと呼ばれる独特の仕掛けを使い、岩礁の穴などにいる根魚(ロックフィッシュ)を落とし込みで狙う釣りです。
ブラクリ
右の写真の上はブラーという名のブラクリ起源のルアー、真ん中の赤い塗装が剥げたのがオリジナル型のブラクリ、下はイガイ風ブラクリです。最近ではアサリ型、カニ型などなど本当に沢山のバリエーションが選べます。
|

ブラクリオモリ各種 |
ブラクリを短くやわらかいリール竿のラインに直結し、青イソメや岩イソメを付けて、岸壁直下、テトラやコンクリートブロックの隙間、岩礁の穴などに落としこみ、当たりを取ります。穴釣りとも言います。足元が期待できないときは、少し沖に投げてしゃくってくる方法も有りますが、根がかり覚悟です。
根魚は落ちてくる餌に興味を示すらしく、何度かひらひらと落とし込んで誘い出した後、ラインを張ってほんの少し底を切るくらいの位置で当たりを待ちます。やや遠くに投げたときは底を切って持ち上げることが出来ないので着底させておきますが、ラインを緩めすぎて放置しておくと、あたりに気付かず根の穴に持っていかれることがありますので要注意です。
エサ
岩イソメ(本虫、岩虫、マムシ)がダントツにお勧めです。一匹が太くて長く、ちょっと値が張りますが、ハサミで切り分けて使え、また硬めの虫なので長めに使えますので、それほど高くもつきません。子供が小さいうちは、付け替えてあげる手間のかからないこの虫を中心に使っていました。ただし、青イソメなどのやわらかい虫の、くねくね良く動く元気なヤツをどんどん付け替えていくのが釣果的には一番かもしれません。 |
カサゴ、アイナメ、メバル、アナハゼなどの根魚やハゼ類が主な釣りものです。ウミヘビと見まごう江戸前てんぷらの高級タネ、ギンポが釣れたことも有ります。
この釣りの面白いところは、なんと言ってもロッドに伝わる微妙な魚信を直接感じながら釣れるところです。そのため、柔らかいライトロッドの方が楽しめます。いるぞ、と思ったところでばっちりゲットできたり、いるはずなのになかなか掛からず時間だけ過ぎた、などといろいろあります。後者の場合、針掛しないくらい小さい餌取りがいただけ、というパターンが多いので、ポイントの見切りも大事です。 |
味噌汁サイズの子カサゴ |
|
攻めの姿勢が我家で良く行くルアー釣りに通じるところが有るからか、子供たちも好きな釣り方で、防波堤に行くとよくやっています。しかし最近はあまり成績は良く有りません。横須賀の海辺つり公園やうみかぜ公園が出来たての頃に、足元への落としこみで面白いように釣れたことがありますが、すぐに釣れなくなってしまいました。首都圏近郊の、釣り人が多くまた入りやすい場所は、ほとんど釣られまくっているというのが現状だと思います。
テトラの隙間が良いポイントになりますが、非常に足場が悪いので、子供がテトラで釣っているときは見えなくなっていないか、気を配る必要があります。小さな子は大事故につながる可能性もありますので、近づけない方が賢明です。大人でも滑って落ちると命に関わります。私たちが小さな子供の頃は、親がなんと言おうと、大海のど真ん中に突き出た消波テトラポッドに、子供だけで毎日勝手に通ったものですが。。 |
| ルアー |
ルアーでは、メバル、シーバス、カマス、青物などが主なターゲットですが、クロダイ、ボラといった大物や降海性のウグイ、メッキと呼ばれるヒラアジ類の幼魚が釣れる事もあります。クロダイは最近はルアーのターゲットとして認知されてきているようですが、なかなか狙っては釣れません。ミノーなどハードルアーも、ワームも使います。
ライトタックルで十分ですし、軽いルアーも投げやすく、釣り味も増します。ワゴンセールの安価なロッドやリールでも悪くはないと思いますが、すぐに良いものが欲しくなるものです。こういったタックルに販売時に巻いてあるラインは太くて巻きグセがつきまくりのものが多いので、これだけは初めから別販売の良いものに巻き変えたほうが良いと思います。
右の写真は、河口の船溜まりでウグイを狙って投げていた渓流用のスピナーにかかった、45cmクラスのクロダイです。私がヒットさせ、ロッドを子供に渡しランディングしました。ほとんど偶然ではありますが、なかなかの獲物です。 |
45cm級のクロダイ |
|
シーバスや青物などは、場所と時間帯・潮回りなどがかなり影響するのでちょっと出かけて手軽に釣ってくる、というほどルアーでの釣果が期待できませんが、カサゴ、アイナメ、メバルなど居着きの魚は居ればそれなりに釣れます。活餌感覚でワームを使うことが多いです。
右の写真はラパラ・ジギングラップ、いわゆるアイスジグです。氷上の穴釣り用だと思いますが、防波堤釣りで足元のメバルなど小型魚を狙うのに最適なルアーです。 |

アイスジグ |
|
| 釣り場 |
東京湾でも相模湾でも、大体どこの港でもOKです。港内に立ち入り禁止の区域もありますので注意します。
相模湾
我家では大磯港、平塚港、湘南港(江ノ島)に良く出かけます。湘南港は若干外海的なので、のんびりサビキ釣りなどをするなら大磯港、平塚港や、江ノ島手前の片瀬漁港がいいと思います。大磯港ならすぐ近くに餌屋さんもあります。
何れの港も一般向けの大きな有料駐車場があります。また広くて足場も良く、家族連れで出かけるのにとても便利です。
三浦半島側だと三崎港、佐島港、秋谷港によく行きます。我家からはやや遠くなるので、こちら方面はのんびりご近所港で防波堤釣りというよりも、エギングなど攻めの釣りやボート釣りが多くなりますが、もちろん防波堤釣りの好ポイントでもあります。この三港以外にも良い港がたくさんあります。
東伊豆
またドライブがてら、といっても前夜車中泊したりしますが、米神、真鶴、熱海、時には網代、伊東まで出かけます。神奈川県内よりは人が少なく、釣れそうな雰囲気が有ります。
我家が伊豆方面に出かけるときは、朝マヅメから昼過ぎまで港で釣りをし、知人のお店がある伊豆高原まで足を延ばしておまけつき昼食を取り、ついでに日帰り温泉に入って帰るという、小市民的贅沢が味わえる日帰り旅行を楽しんでいます。家族サービス込みなら、いろいろオプションが選べる方面です。
東京湾
東京湾側は海釣り施設が充実しています。磯子海づり施設、横須賀海辺釣り公園、横須賀うみかぜ公園などが我家のスポットです。海釣り施設の類は岸壁際の鉄柵が好きではないのですが、安全面から言うと小さな子供連れ向きです。
横須賀海辺釣り公園でお湯を沸かしてラーメンを食べていたら、「禁止ですよー」とスピーカーで叱られたことがあります。おそらく殆どの公園では火気禁止だと思います。気をつけましょう。また基本的に投げ釣り禁止というところもあります。 |
| その他 |
毒魚
防波堤など沿岸の小物釣りで、ハオコゼという小さな魚が釣れることが有ります。こやつのひれにある毒針に刺されると、小さな体に似合わずめちゃくちゃ痛くなります。半日くらいは悶絶することになりますので注意下さい。かく言う私も経験者で、著作権フリーの画像が無くここに掲載できないのが残念ですが、その姿かたちを一度覚えておくと良いです。その他に、有名な毒魚のゴンズイも良く釣れます。磯魚のアイゴも毒魚として有名で、防波堤に群で寄ることがあります。投げ釣り仕掛けやルアーにアカエイが掛かることもまれにあります。
これらの毒魚の毒は熱に弱いそうで、やけどしない程度の熱いお湯につけると、毒が変成して痛みが和らぐそうです。釣り場に運よくお湯があることを祈ります。近くのコンビニに駆け込んで、カップめん用のお湯を貰うといいかも。
ハオコゼやゴンズイが釣れたら、長めのプライヤーで針を外すか、外しにくければやむを得ないのでハリスを切ってしまいます。トングや火バサミのような形をしたメゴチバサミもあると便利ですが、ヌルで滑らないようにトゲトゲが付いていますので、リリースする魚にはあまりよろしくありません。ちなみにゴンズイは味噌汁などにしておいしい魚だそうです。
|