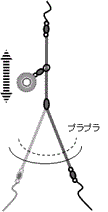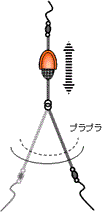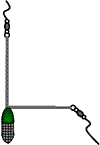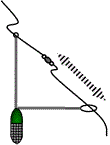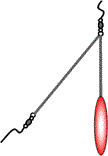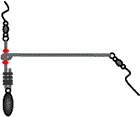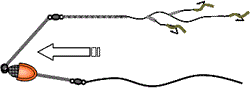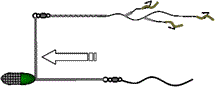投げ釣り 相模国野外育児記~海釣り編・相模湾、東京湾の釣り
ホーム > 釣り・海 ~ 投げ釣り
| 投げ釣り | |||||||||
|
|||||||||
| タックル | |||||||||
| ロッド、リール 15号~30号くらいの重いオモリを遠投しますので、専用の投げ竿を使います。専門に取り組むのでなければ比較的安価なものでも大丈夫だと思います。というのは我家がそうだからですが、やはり遠投性など性能は価格に比例してしまいます。 リールも遠投専用にスプールの大きなものが売られていますが、ある程度の大きさがあれば他のスピニングリールを兼用しても大丈夫です。小さなスピニングリールや、浅溝タイプのスプールでは糸巻き量が足りない場合があります。 仕掛け 幹糸の先に1本と、エダス2本の合計3本針が標準です。4本、5本とたくさん並んでいる仕掛けも使われます。市販の仕掛けセットは、絡みにくいように幹糸の上部が2本縒りになっていて、またエダスの根元に軟質プラスチックのパイプが通してあります。 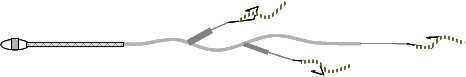 私が子供の時分にもすでに市販の仕掛けセットはありましたが、それでも苦心惨憺ナイロン糸を縒り合わせ、いろいろ工夫して3本針仕掛けを自作して出かけたものです。最近は、投げ釣り仕掛けの自作はおろか、中空のアイの無い針にラインを結ぶこともほとんどなくなってきました。 天秤 オモリは天秤と言われるワイヤで作られた道具とセットで使います。仕掛けの絡み防止、食い込みの向上、向こうあわせのため、など色々な目的が有ります。形やタイプが様々あり、遠投性能を重視するか、絡み防止を重視するか、などで選択します。元々天秤と一体のもの、ナス型オモリをセットするものなどの違いも有ります。 一番重要な機能は、キャスト時にハリス、幹糸と道糸が絡まないようにすることです。空中を飛行している間は当然一番重いおもりが先頭を飛んでいますが、天秤のおかげで幹糸・ハリスと道糸の飛行軌道が離れ、絡みにくいという仕組みだそうです。 天秤には色々な種類があって、使い慣れたお気に入りができるまでは選択に悩んでしまいます。あまり神経質に選択することもないかも知れませんが、投げ釣りでは重要な要素とされています。自作でのめり込む方もいます。受け売りですが、一般に使われているものを紹介します。我家では、サーフでは遊動式の海草天秤かジェット天秤、防波堤のちょい投げでは小さな片天秤を主に使っています。 |
|||||||||
主な天秤の種類
この他、根掛りが多い場所などで胴突き捨ておもり式を使われる方もいます。おもりが胴突き仕掛けの先端についていて、根掛り時はおもりだけ切って捨てます。 |
|||||||||
| 遊動・固定 遊動式天秤はハリス側にラインが自由に伸びるため、魚から見て違和感が少なく食い込みがいいと言われています。置き竿にする場合や、カレイなどのようにある程度食い込んでからあわせを入れる場合に有利のようです。L字型の天秤の多くで、遊動式と固定式の2つのタイプが見られます。名古屋天秤やジェット天秤のように腕の連結部分が固定されていないタイプでも、腕にラインを固定せず遊動式と同じ仕組みになっている天秤もあります。 固定式はキャスト時の安定性で絡みにくいことと、てこの原理であたりが取りやすく、手持ちでさびきながら釣る場合に有利だそうです。私自身はあたりの取りやすさという意味ではあまり実感できません。 半遊動式はおもりが天秤の腕に固定されておらず片腕の長さ分だけ移動します。その分、遊動式と同じく食い込みがいいと言われています。名古屋天秤、ジェット天秤などの半遊動式はキャスト後は腕と仕掛けが一本に延びるので、根掛り防止にも有利です。但し遊動式のところにもあるとおり、腕の連結部分が固定されていないタイプで、ラインを固定せず遊動式になっているものもあります。 飛行想像図 こんな感じで飛んでいるのではないかと思います。ハリスと道糸が別軌道を飛んでいるので絡みにくくなっています。
|
|||||||||
|
キャスト後、少しづつ仕掛けを曳いてきて、海底に変化がある場所で当たりを待つ方法で釣りますが、置き竿で待ってもある程度釣れます。置き竿にするときは、ロッドスタンドに竿を立てかけておくとアタリが見えやすく便利です。スタンドにも、砂浜に突き刺して使う一本足のタイプや、3-4本を一緒に立てかけられる自立式など色々有ります。 置き竿であまりにも長く置いておくと、フグにハリスを切られて無くなっている事が良くあります。また仕掛けが海底で揉まれて絡んでしまうことも有ります。シロギスなら適当に聞き合わせしながら曳いてくるほうがいいです。 砂浜から遠投する場合、投げる際に切れにくい青イソメが主に使われます。またカレイの場合はカレイの好む岩イソメ(岩虫、本虫、マムシとも)が使われます。合成餌であるバイオワームというものも売っていて、一つ買っておくと便利かもしれませんが、あまり釣れた記憶が有りません。 |
|||||||||
| 釣り場 | |||||||||
| シロギスなら湘南海岸、西湘海岸一帯の砂浜が主な釣り場ですが、三浦方面でも東京湾でも可能です。我家では大磯の海岸が主です。休日には、大磯から小田原方面にかけて、たくさんの釣り人が並びます。 東京湾側の岸壁では、秋から春にかけてカレイ釣りが盛んです。我家では金沢区の福浦岸壁に良く行きます。 |
|||||||||
| その他 | |||||||||