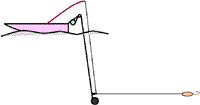レイクトローリング 相模国野外育児記~淡水釣り編・神奈川の川と湖の釣り
ホーム > 釣り・川、湖 ~ レイクトローリング・ハーリング
| 釣りものボートタックル(レイクトローリング)タックル(ハーリング) タックル(ヒメトロ)その他のタックル 服装・防寒 芦ノ湖のレイクトローリング釣り方・操船安全対策 |
||||||||||||||||
| レイクトローリング・ハーリング | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| レイクトローリングでもある程度の浅場を探っていくことはできますので、解禁当初から楽しめます。我家では、朝一番はキャスティングとお土産確保の餌釣り、日が昇りかけたらトローリング、というパターンになっています。 神奈川県内では芦ノ湖以外では聞いたことが有りませんが、中禅寺湖、銀山湖や、北海道の各湖沼など、関東以北で広く行われているようです。我家は芦ノ湖専門ですが、いつか是非中禅寺湖、銀山湖にも遠征したいと思っています。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| レイクトローリング > 釣りもの | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ヒメマス サイズは30cm程度ですが、銀色のきれいな魚体の魚です。芦ノ湖ではヒメペラという特殊な集魚器を使い、群れを追ってトローリングするヒメトロが行われています。富士五湖などでは、アミの撒き餌とサビキ仕掛けをつかった釣りが行われていますが、芦ノ湖では禁止の由。我家ではあまりヒメトロをやらないので残念ながら写真が手元にありませんが、レッドコアのトローリングにもたまにヒットします。 サクラマス、サツキマス それぞれヤマメ、アマゴの降海型の大型魚で、放流も行われているようです。数は少ないらしく、時期・時間・レンジなどをしっかり狙って釣る必要があるようです。残念ながら我家では実績ゼロです。 イワナ サクラ・サツキ同様、放流も行われています。最近の特別解禁で、スプーンのキャスティングで20cm級が1匹釣れましたが、トローリングでは実績がありません。 |
||||||||||||||||
| レイクトローリング > ボート | ||||||||||||||||
| たくさんあるレンタルボート屋さんで借りることが出来ます。通常はエンジンボートやエレキを付けた手漕ぎボートを使います。手漕ぎだけでも不可能ではないですが、長時間はできませんし、少し風があるときなどはボートが流されて釣りづらくなります。エンジンボートが断然有利です。 実際、我家のホームゲレンデの芦ノ湖では、日が高くなるにつれて南風が強くなることが多く、手漕ぎ、或いはエレキでも、仕掛けが(実際はボートが)大きく右又は左に流されたり、岸近くに押されたり、或いは向かい風のときはボート速度が落ちて仕掛けが沈み、根がかりしたり、ということが多くなります。こんなときはのんびりしたひとときなどはとても楽しめません。 |
||||||||||||||||
| 小型船舶操縦士免許 エンジンボートのレンタル、エレキの使用には、ボート屋さんで小型船舶免許の提示が必要です。芦ノ湖では、エレキ使用時は慣習(たぶん、です)として提示を求めないようですが、万一のことも考えられますので無免許は避けましょう。但し最近の法改正では3m未満の船と2馬力以下のエンジンなら免許不要とされているようなので、ローボート+エレキなら不要かもしれません。 また小型船舶操縦士は船長免許で、その指導の下で無免許の操縦者による航行ができると教わりました。我家でも安全な場所では子供に操縦させ、ヒットするまで親父はのんびり休憩などということもしていました。詳細は未確認ですが、最近の法改正では、河川等の狭く危険な場所ではこれが出来なくなっているようです。芦ノ湖は、海賊船をはじめ大型の旅客船が多く、また超高速のプレジャーボートがぶっ飛んできたりしますので、無免許者の操縦はやめたほうがいいでしょう。最近の法改正に関しては私自身詳しくないので、別途調べてみてください。 私の場合、湖でエレキを使うために四級小型船舶を取得しました。当時の四級、現在の二級免許は、ヤマハなどの教室に申し込むと、数日の教習と試験で簡単に取ることができます。十万円前後の費用はかかりますが、一生もの(更新講習がありますが)ですのでお勧めします。 |
||||||||||||||||
| レイクトローリング > タックル(トローリング) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ラインシステム レッドコアライン、ドジャーといった専用のライン・道具を使用することや、一日中ラインを引きずり回すことなどから、レイクトローリング専用のラインシステムを組む必要があります。我家での典型的なラインシステムの例は次の通りです。
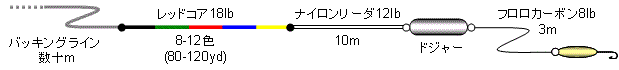 実際の釣果はルアーとのバランスや、天候・水温など、あらゆる条件の組み合わせで決まりますので、ラインシステムのパラメータもその時々で柔軟に変えてみて最適値を探すようにすると理想的です。 レッドコア 中心(コア)に鉛(レッド)のワイヤを使い、カラーの編み糸で被覆した重く沈みやすい専用ラインです。ネットでも買えますし、湖のボート屋さんにもあります。町の釣具屋さんだとあまり見かけません。 レッドコアラインには、12/15/18/27LB(ポンド)など、幾つかの種類がありますが、一般には18ポンドが使用されます。我家ではこれ以外使用したことがありません。ラインは10ヤード(9mほど)毎に色分けしてあって、10ヤード(一色)当たり1.5m~2mくらい沈むそうです。レイクトローリングでは、魚がいそうな層、つまり仕掛けを引っ張るレンジをこの色数で換算して表現します。5色分、50ヤード出すと、水面下約7.5~10mの層を引くことになります。今日は5色で釣れました、などと言います。ボート屋さんでは、今日の有望レンジを色数で教えてくれます。 出来るだけ広いレンジを探るために、複数出してあるロッドでそれぞれ色数を変えて曳いています。もちろん一方のタナにヒットが集中すれば、同じ色に合わせることもあります。
リーダー レッドコアとドジャー又はトップライン(ハリス)の間に、10m程のラインを入れます。動きが悪く目立ちやすいレッドコアと、ルアーの間を離す効果が有ります。ナイロンモノフィラメントが扱いやすく、また針掛を良くするクッションの効果も有るようです。PEを使う方もおられるようです。我家ではナイロン12ポンドです。 ドジャー
小さな魚がつれたときは、レッドコアとドジャーの抵抗で釣れた感がほとんど無いこともあります。結果として有り無しどちらとも言いがたいので、我家では1本は有り、1本は無しの2本立てでやってます。釣り味が削がれるので、個人的には無ドジャー派です。 ハリス 我家では6ポンド~8ポンド程度のフロロカーボンを使用します。普段は2ヒロ(約3m)ほどとっているつもりですが、両腕以外では測っては無いので、正確な数字ではありません。ラインはドジャーまでしか巻けませんので、ハリスをあまりにも長く取りすぎると、巻き切っても魚が寄ってきてないという事態もあり得ます。ロッドよりやや短めを目安にしていますが、60cm~100cm程度が、視覚的、アクション的にドジャーの効果が出やすいそうで、あたりが遠い時はグっと短めに調整して試してみるといいでしょう。 ラインはナイロンでもかまいませんが、レイクトローリングではルアーが水中で回転してしまい、ほんの数十分でハリスがグリグリ巻きになることがあります。また底を引いてしまったときに傷が付くことも有り、固めのフロロカーボンが有利と思い使用しています。大物を期待するなら太目のラインが必要ですが、そこは試行錯誤になります。 スイベル ドジャーの前後には大型のスイベルが付いていますが、念を入れて1個スイベルを追加しています。ドジャー抜きでリーダとハリスを直結する場合は、ボールベアリング入りなどの小型高性能スイベルをつけます。ルアーが回ってしまったときは一発でハリスが死亡しますので、スイベルはケチらずに高性能タイプが良いです。海釣りで使う多重連結スイベルも良いかもしれません。 ルアー側も直結は避け、スナップスイベルを入れたほうが良いと思います。スナップスイベルでウェイトバランスやシルエットが変りますので、出来るだけ小さいものがいいと思います。 |
||||||||||||||||
|
ルアー プラグ、スプーンの何れもOKです。とっかえひっかえ使ってみてその日のヒットルアーを探します。
ルアーいろいろ
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| フック レイクトローリングは向こうあわせ(魚がバイトし反転するときに勝手に掛かる)なので、フックは細く鋭いものに交換したほうが有利です。バランスの問題がありますが、プラグのトレブルフックはトラウトの硬い口に弾かれやすく、シングルに替えたほうが良いという説も有ります。 またスプーンにフックを直結すると、トラウトが首を振ったときにフックが刺さった部分にテコの原理で力がかかりやすく、外れやすいため、一旦フックを糸に結んでルアーに取り付けるほうがいいようです。長さの違うシングルフックを2つ付けておくと、一方は口に、もう一方はエラに掛かり、安心して取り込めることがあります。実際にどんな方法がベストか数値的な証拠はつかみにくいですが、いろいろ試しています。 鯉の吸い込み仕掛けに使われるケプラートなどの強度のある編紐をシングルフックのハリスに使い、2本を組み合わせたチラシ針というフックセットが良く使われます。淡水用の小さなものから、海のジギング用の大きなものまで、市販されています。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| レイクトローリング > タックル(ハーリング) | ||||||||||||||||
| 専用のタックルがあるとは聞いたことが有りませんが、通常のフライタックルをボートで引っ張ると思えばいいと思います。水面下を狙うのでシンキングラインを使用しますが、ボートで引くとエクストラファーストシンキング(IV)でもさほど沈みません。レッドコアを使う方もおられるようです。 我家では芦ノ湖のキャスティング用に買った#8ロッドと、ハーリング専用に沈む速度の速いエクストラファーストシンキングを巻いてある#7-#8のリールの1セットだけ使用しています。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| レイクトローリング > タックル(ヒメトロ) | ||||||||||||||||
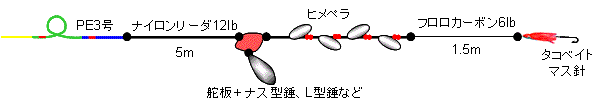 |
||||||||||||||||
| レイクトローリング > その他のタックル | ||||||||||||||||
タックルボックス バスフィッシング用の普通の大型タックルボックスを使っていますが、ABUのリールからルアーまで、レイクトローリング・ハーリング専用のタックルがこれ一個に全部入り、便利です。大きいといえば大きいですが、トローリングの場合はあれこれ道具がかさばる割には、車からボートまで運べば後は持ち歩くことは無いので、重宝しています。2階建ての2階部分右サイドに魚探がピッタリはまるように細工してあります。
我家では、葵ソニックのエスペランサーPRO-32という魚探を使っています。あまり高級品ではないですが、カラーでGPSマップ付きという優れものです。釣果に直結しているかどうかは怪しいところですが、いま80cm級がいた、とか、すごい群れが見えた、など、船上での盛り上がりネタの一つにはなります。
エレキ
エレキは、ガソリンエンジンと違って推進力がポンド(LBP)で表されます。一般的な12V仕様のものであれば50ポンド前後ですが、これで十分です。トローリングの航行速度は徒歩レベルですので、30ポンド位でも問題ないですが、風があるときなどはパワーが欲しくなります。
バッテリー
ワニ口クリップ エレキや魚探のバッテリー接続用端子部分には、ワニ口クリップや丸くて穴の開いた端子が付いていますが、丸型端子の場合、取り付け時にバッテリー端子の蝶形ネジを一旦全部外さなければならず、うっかりすると落ちてどこかにいってしまいます。丸型端子の先を切って開けるか、先開きタイプに替えると便利です。我家では端子を全部大き目のワニ口クリップに替えて、ネジを回すことなく取り付けられるようにしています。これだと、レンタルのエンジンボートのバッテリから魚探の電源を拝借するのにも便利です。 ショート注意 車のバッテリーでも同じですが、電極端子間のショートに十分注意する必要があります。ランディングネットの枠や柄、導電性のあるロッドなどが触れるとスパークする恐れがあり、最悪溶けます。火傷の危険もあります。我家ではキャンプ用の折りたたみイスの金属部分でショートし、小さめのイスだったので細いアルミパイプが溶けて千切れたことがあります。電圧が低くても相当な放電能力があり、恐るべき電流パワーです。電極端子のプラスチックカバーが製品に付属していますので、普段から無くさないよう付けたままにしておいたほうがいいと思います。ウチのはもう無いです。 余談ですが、マリンバッテリーは容量たっぷりで放電しきっても劣化が少ないので、我家では、キャンプでテント内の照明にしている乾電池式12V蛍光灯ランタンの電源として重宝しています。車と同じ電圧ですので、携帯充電器など車用アクセサリが車から離れてもテント内やテントサイトで使用できます。バッテリからはワニ口クリップでシガーライターソケット形式の分岐器を接続します。先述の蛍光灯ランタンは電源引き出しの改造が必要でしたが、電源線にはシガーライターソケットが付けてあり、分岐器経由でバッテリに簡単に繋がるようにしてあります。もっとも、最近はハイブリッド車が普及してきたので、アウトドアでの電気機器使用が容易になってきているみたいです。 |
||||||||||||||||
| レイクトローリング > 服装・防寒 | ||||||||||||||||
| 芦ノ湖の解禁日は3月1日、その前週の2月の土日に特別解禁が行われます。真冬です。箱根は氷点下です。年によっては暖かい雨が降ったりしますが、よく晴れた日であれば、すぐにロッドのガイドが凍りつく程の低温になります。 服装・ホッカイロ 暑ければ脱げばいいので、防寒は十分に行いましょう。意外に薄くなりがちなのが下半身の方です。モモヒキがあるとだいぶ違います。一通り着込んでさらにウェーダーをはくと、風を通さず、つま先まで一体空間が出来ますので暖かくなります。すぐに成長する子供のウェーダーまで買えないやということであれば、通常の防寒ズボンでも大丈夫です。 背中とおなかの下着の上に、貼るタイプのホッカイロを付けておくと、これもかなり違います。つま先に張るタイプも効果的です。昔はモミモミするタイプ一つで、せいぜい貼るタイプが出てきたくらいでしたが、ここ最近は両肩を覆うタイプの貼るホッカイロ、手に塗るジェル状のホッカイロなど色々とバラエティに富んでます。但しこれらの効果はちょっと疑問でした。 釣りですのであえて言うほどのことではありませんが、防寒着が完全防水でなければ雨具も必須です。芦ノ湖では、真冬でも雨が降るときは快晴時よりも気温は高いので、風がなく小雨程度なら十分釣りができますが、雨具がなければ凍死します。子供の分も忘れずに。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 手袋 極寒時は手袋も必須です。キャスティングの場合は、小指と薬指以外は先が現れている釣り用手袋が必要ですが、トローリングだけなら通常の手袋でも何とかなります。 フローティングベスト ボート釣りではフローティングベスト、救命胴衣の着用は必須です。ボート屋さんで貸してくれますが、子供と釣りに行く場合にはこれでもかというくらい安全を第一に考えるべきですので、他でもいつでも使えるようにサイズの合った浮力の強いものを自前で準備するほうが良いかもしれません。 トイレ袋 レンタルボートには、業務用スープの空缶の簡易トイレが置いてあることが多いです。女性は厳しいですが、男性ならコレで用を足すことが出来ます。しかし完全にチ○●をズボンの外に出さないと失敗する可能性が高いので、厚着の時分は結構大変です。ウェーダーだとなおさらです。ドライブ用のトイレ袋だと少し使いやすく、一つ持って行くと安心です。 ホットドリンク 寒い時期は水筒にホットココアなど温かく甘い飲み物を用意しておくと、しばし生き返ります。子供が寒くてどうしようもない様子のときは、あまり我慢させずに上陸させましょう。風邪をひいてはバカらしいですし、つらい遊びであるというイメージだけが染み付いてしまいます。子供が小さいうちは、4月以降の、暖かくなってからの時期に始めたほうが良いかもしれません。 |
||||||||||||||||
| レイクトローリング > 芦ノ湖のレイクトローリング | ||||||||||||||||
| 2月の特別解禁、3月の解禁から、12月の禁漁まで、1年中楽しめます。 放流を行っている期間はうまくポイントに入れば入れ掛りの可能性がありますし、解禁時放流の超大型魚の釣れ残りに当たることも有ります。毎回とはいきませんが、ウチの子供たちも50cm級の元気なトラウトを釣っています。 晩春以降、深場に落ちてからはトローリング以外ではなかなか釣れなくなります。夏の暑い時期から禁漁にかけてもトローリングは可能ですが、放流を行わないこともあってか、可能性はかなり下がります。我家では、夏の芦ノ湖はバス釣りの方が主となります。秋以降はワカサギ釣りを楽しみ、釣れたワカサギの生き餌でトラウトを狙うムーチングができます。これが結構大物を狙えますが、我家ではあまり大物の実績はありません。 トローリングで完全なボウズで終わることはあまり無く、キャスティングよりも釣果は高いと思いますが、正直なところ、小さいの2-3尾で終了!、ということはよく有ります。子連れの釣りは楽しくないと意味が無いので、朝夕は餌釣りやワカサギ釣りやエサ釣りでなんとかお土産を作っておいて、日の高いときはトローリングという方法もお勧めです。我家では、瓶入りの油漬けイクラ餌、マス針、ワカサギ仕掛けなどをタックルボックスに入れておき、いつでも切り替えて楽しめるようにしています。 |
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
入漁料 芦ノ湖で釣りをする時は、ボート釣りであるか陸釣りであるかに関わらず、入漁券の購入が必要です。ボートを借りる場合はレンタル料と一緒に支払います。年券もあります。中学生以下は無料なので、子連れには大変助かります。 |
||||||||||||||||
| レイクトローリング > 釣り方・操船 | ||||||||||||||||
| 実績の怪しい我家が講釈するのもはばかられますが簡単に。優良情報はネット上や書籍類にたくさん有りますのでそちらもどうぞ。 速度 ボートの速度は諸説有りますが、我家では大体人が歩く程度のスピードです。スロットルを全くひねらないアイドリング状態でもスクリューは回り、この状態で進めると歩く速度になります。逆風のときはスロットルで速度を調整します。風で流される分、相対速度が落ちてラインが底を引いたりしますので、要注意です。 仕掛け出し タックルをセットしたら、リールのスプールとクリックボタンをフリーにし、ボートを進めながらレッドコアラインを目標色数まで出していきます。手で引き出しながら1-2色出せば、あとは水の抵抗で勝手に出て行きます。ドジャーをつけていれば比較的簡単に出てくれます。早く出したい時はボートの速度を上げてやります。勢い良くラインが出ている時はバックラッシュ(重いレッドコアの慣性により、スプールの回転速度がラインの出るスピードを上回って、絡んでしまう)しないよう、注意します。レッドコアが絡むと中の鉛線がキンクしやすく、最悪鉛線だけ切れてしまいます。 目標色数分が出たら、手でいったんスプールを止め、クリックを入れます。大き目のリールなら、クリックとメカニカルブレーキ(リールの横についている丸いノブ)の抵抗で、仕掛けを曳いている状態でもラインが出ず、魚がかかった時点でラインが出て行きます。曳くだけでラインが出て行ってしまう場合は、メカニカルブレーキを締めます。 小さめのリールだとメカニカルブレーキやクリックの抵抗が低く、ラインがうまく止まらないときがあるので、この場合はスプールをロックし、スタードラグを緩めます。曳いてもラインが出ず、魚がかかった時にだけ出て行く程度にドラグを調整します。ヒットしたときにはドラグを適切に締めなおす必要があります。 ロッドのセット ロッドは船の両脇から2本を張り出し、ホルダにセットします。ホルダを調整しロッドを水平方向から若干上に向け、また真横から若干前側に出すと、ロッドの曲がりを含めてちょうどいい位置になります。あとはトロトロと低速で引っ張ります。 操船 ボートのスピードを変えた時や、方向を変えた時などにヒットする確率が上がるといわれます。ルアーの動きに変化が起きるためと思われますが、なかなか実感するには至っていません。 岬の先端付近のような地形が好ポイントだそうです。芦ノ湖だと湖尻の亀ヶ崎などが有名です。岬の根元方向から先端方向に向かって平行して進み、先端を過ぎたらくるっと後ろ向きに1回転し、反対側の先端から根元に向けて平行に引く、といったテクニックが書籍やネットで紹介されています。が、まあそればっかりやってても疲れますので、我家では付近を通るときにやってみるくらいです。 何十メートルも後方に仕掛けを引っ張ってますので、方向転換のときはなるべく大きく回ります。急に曲がると内側のタックルのラインが着底して根がかりしたり、外側のタックルのラインがプロペラに巻き込まれたりなどのトラブルが起きます。どうしても急に曲がる必要がある場合は速度を上げて回ります。プロペラにラインを巻き込んだ時は、とにかくエンジンをストップし、もう一方の仕掛けを急いで巻き上げましょう。一旦巻き込んだラインは傷が付いている可能性が高いので、見た目OKでも涙を呑んで交換しましょう。方向転換のとき以外にも、風でボートが流されている場合など、一方のラインがボートに近づき巻き込みの危険性が高くなることが有ります。 風の影響は非常に大きいので、注意が必要です。我家でも、湖底の状況に不案内なうちは、知らず知らずのうちに浅場に流され、根がかりしたこともしばしばありました。 またマナーとして、他のボートに近づきすぎたり、他のトローリング仕掛けの近くを横切ったりしないように注意します。陸っぱりのキャスティングの人がいる場合は、近づかないようにくれぐれも注意します。石を投げられるかもしれません。 他船と至近ですれ違うときの右側航行(相手を左舷に見る)や交差時の航路優先権などの原則は湖でも当然守ります。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 相手が湖底ではなく魚なら、既に向こうあわせでフッキングしているはずですが、ロッドをホルダから外す前に、スプールのロックをオンにします。このとき追いあわせされます。またロッドをホルダから外す時などにラインテンションを緩めないように注意します。仕掛けが長くロッドも柔らかいので、不用意に扱うと、フックが結構簡単にスカっとはずれてしまいます。 ランディング 小さな魚でもはじめは強烈に引き、途中で妙に軽くなることがあります。それでもあきらめずに一旦巻き上げます。やっぱり付いていたということも多いです。魚ではなく底を引いていた場合には藻やごみが付いていることが多く、それを取らなければ永久に釣れません。結果的には時間の無駄を無くすことにつながりますので、面倒くさがらずに(かなり面倒ですが)最後まで巻いてフックをチェックするほうがいいです。 最後は、ロッドを寝かし過ぎないようにし、ロッドの操作で魚を寄せてきます。なれないとリーリングだけで寄せてしまいがちです。ハリスの長さを十分とっていれば問題ないですが、最後の取り込み時にラインの余長が足りない場合にはロッドが立てられず、寄せきらないということもあります。やむを得ずということで不用意にラインを出すと、そこでバレてしまう可能性大です。逆にハリスが長すぎると、ドジャーまでしか巻き取れませんので竿を限界まで立ててもやっぱり魚がよってこないということもあり得ます。 レイクトローリングは向こうあわせに頼るせいか、フッキングが浅いことが多いと感じます。フックのかかり具合が不安なら、よほど小さいものでなければ水中にいるうちにネットで取り込んだほうが良いと思います。 |
||||||||||||||||
| レイクトローリング > 安全対策 | ||||||||||||||||
| 風 エレキや手漕ぎの場合、風が強くなると桟橋まで戻れなくなる可能性があるので、遠出のときは要注意です。芦ノ湖では、朝方無風でも、日が昇ると南風(箱根から湖尻方面)が強くなることが有ります。解禁直後は春一番の季節でもあり、今日はあったかくてトロ日和だなァと思ってたら突如ミニトルネードに見舞われたこともあります。強風で戻れなくなった場合は、携帯電話でボート屋さんに連絡し引っ張ってもらいますが、別の桟橋につけることが出来ればそこに一時退避してから連絡してもいいでしょう。ムリは禁物です。 携帯電話を忘れずに持参し、普段からボート屋さんの番号を登録しておきます。強風だけではなく、プラグのかぶりや燃料系統の故障など、エンジンの不調でボート屋さんに救出を依頼しなければならないこともあり得ますので、携帯は必須です。我家でも実際、エンジンが始動しなくなり救助してもらったことがあります。このときは解禁釣り大会の真っ最中で、現場まで代わりのボートを引いてきていただき、そのまま戦闘続行できました。感謝。 霧 芦ノ湖では、強風の他に、山上湖だけあって濃霧が発生することがよく有ります。自分の位置を見失うのはとても危険ですし、また岸近くに寄ってしまい、キャスティングの仕掛けが飛んでくる危険性もあります。霧のときは無理な出航はやめ、沖に出てから心配になったなら早めに桟橋に戻りましょう。こんなときは、霧が晴れるまで桟橋近くでキャスティングや餌釣りをします。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
自船内 自船内での注意も必要です。エンジンボートは大きいので比較的安定していますが、それでも船内で動き回るとかなりゆれます。また冬の早朝船内が凍っているときや、濡れているとよく滑ります。子供のうちは危険察知が甘いので、転落しないように親が十分注意してください。大人が転落する場面も見たことが有ります。水温が摂氏数度のときに落水すると、沈んでしまうことは無くても、低体温で命に関わる事態も十分想定されます。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||
| ニジマスもヒメマスも美味しい魚なので、よほど小さいもの以外は持ち帰らせてもらって全部家で食べています。ニジマスは小魚のうちは白身ですが、大物はピンクのサーモン色をしています。大きさの問題か、エサの問題かはよく分かりませんが養殖魚は白く、野生魚は赤いというふうにも聞きます。 小さいのは内臓を出して丸焼きに、大きいのは三枚におろしてムニエル(塩コショーと小麦粉をまぶしてバター焼き)にすると良いです。少しカッコつけてハーブとかスライスアーモンドとかをまぶすと本格的な感じになります。私は多目の塩だけで塩ジャケ風にするのが好みです。 内蔵を出した後、腹腔の上部、背骨の下部分にある黒いドロドロを爪で剥ぎ取ります。これはニジマスの腎臓で、塩辛にするとメフンという極上の珍味になるそうですが、肉だけ食べるときはきれいに除去してしまいます。何事も面倒なことには興味を示さない次男と違って、長男は三枚おろしから出刃包丁とぎまで全部やってくれます。 |